| ☆5.0 | ☆4.0 |
| 1926 メトロポリス 米 No.18 | 1940 フィラディルフィア物語 米/ J・スチュワート |
| 1947 海の沈黙 仏 No.25 | 1945 ミルドレッド・ピアース/米 J・クロフォード |
| 1952 お茶漬の味 小津安二郎 | |
| 1957 めぐり逢い 米/D・カー | |
| 2017 ラッキー 米 No. 15 | 1963 地下室のメロディー 仏/ギャバン、ドロン |
| 1968 銀河 仏・伊 No.10 | |
| 1970 大空港 米 B・ランカスター | |
| 1971 アンドレイ・ルブリョフ 露 No.5 | |
| 1972 ブルジョワジーの秘かな愉しみ No.10 | |
| 1972 ゲッタウエイ No.29 | |
| 1973 さらば冬のかもめ No.20 | |
| 1984 プレイス・イン・ザ・ハート 米 No.17 | |
| 1984 ナチュラル 米 No.7 | |
| 1984 バーディ 米 No.8 | |
| 1984 空海 /北大路 欣也 | |
| 1987 ザ デッド アイルランド、英、米 No.24 | |
| 2007 ブレードランナー FC 米 No.16 | |
| 2009 しあわせの隠れ場所 米 No.2 | |
| 2009 100歳の少年と12通の手紙 仏 No.14 | |
| 2012 チョコレートドーナツ 米 No.9 | |
| 2012 東京家族 No.34 | |
| 2014 グローリー 米 /キング牧師の行進 | |
| 2014 アゲイン28年目の甲子園 | |
| 2015 黄金のアデーレ 米英 No.6 | |
| 2016 この世界の片隅に 日 No.12 | |
| 2017 ギフテッド 米 No.1 | |
| 2017 三度目の殺人 No.31 /是枝裕和 | |
| ☆4.5 | |
| 1983 ノスタルジア 伊、露 No.3 | ☆3.5 |
| 1972 故郷 山田洋二 No.33 | |
| 1956 早春 小津安二郎 | nお1955 泥棒成金 米 ヒッチコック |
| 1957 東京暮色 小津安二郎 | 1960 ローラーとバイオリン 露 No.4 |
| 1980 遥かなる山の呼び声/山田洋二 | 1964 奇跡の丘 伊 パゾリーニ |
| 1991 息子 山田洋二 No.35 | |
| 2016 manchester by the seaNo.13 | 1965 エルダー兄弟 米 |
| 2018 万引き家族 No.23 | 1973 ソイレント・グリーン 米 |
| 1979 テス 英・仏 No.26 | |
| 1975 バリー・リンドン 英 S・キューブリック | |
| 1977 スラップ・ショット 米 J・R・ヒル | |
|
☆3.0 |
1984 1984 英/ 未来小説を当該年に映画化 |
|
1988 カクテル 米/T・クルーズ |
1985 緑の光線/仏 No.22 |
| 1988 アキラ SFアニメ大作 | |
| 1990 グッドフェローズ 米/スコセッシ | |
| 1992 木と市長と文化会館/仏 No.21 | |
| 2001 ビューティフル・マインド 米/ナッシュ理論 | |
| 2004 サン・ルイ・レイの橋 西英仏 No.27 | |
| 2011 そして友よ、静かに死ね 仏/ロマ強盗団 | |
| 2012 カルテット 米/D・ホフマン | |
| 2013 グランド・マスター 香港 No.19 | |
|
2014 キングスマン 英/C・ファース |
|
|
2015 あん No.30 |
|
|
2017 君の膵臓を食べたい No.28 |

No.35
息子
1991/121分
山田洋二 監督 椎名誠 原作
三国連太郎、永瀬正敏、和久井映見、原田美枝子、浅田美代子、いかりや長介、中村メイコ、奈良岡朋子、田中邦衛
原作は椎名誠の「倉庫作業員」1991(ハマボウフウの花や風)で27年前の作品だが、何かもっと古い時代の話のように見える。それだけ時代が大きく変わったのか、作者のイメージそのものがもっと古い時代を想定していたのかは定かではないが、作り物の匂いがするのは何故だろう。
一つには現時点では、田舎と都会の生活の差があまり無くなったことかもしれないし、設定された岩手の山間も今は多分限界集落で、描かれているような温かい地域社会も崩壊しているのではと思われてならないかもしれないからだ。
でもこんな事を感じさせるのは、製作者側の問題ではなく、時代が変わったという事で、もっと早く見ればそれなりの実感がわいたのだろう。映画にも賞味期限があるものもあるという事がわかる。
田舎を出た青年が都会に老父を呼ぼうとしても来ないし、結局田舎で孤独死を迎えるのも、
最早避けられないものとして、普通にある。
親は自分のことより、息子が幸せでありさえすれば幸せなのだ。
その一番の心配であった次男が、世間体に囚われず人間として素晴らしい聾の娘を娶る決意をしたことに、人間としての成長を確認して安堵する真夜中の缶ビールのシーンは、三国の名演技と共に一番の見どころとなった。
予定調和路線と言えばそうだが、本作も安堵感溢れる作品だった。

No.34
東京家族
2012/146分
山田洋二 監督
橋爪功、吉行和子、西村雅彦、夏川結衣、中島朋子、
林家正蔵、蒼井優、妻夫木聡
小津作品の中でも傑作と思われる「東京物語」のリメーク。果敢に勝負に挑んだ山田監督に敬意!
小津作品は、親子関係の時代変化による親の哀歌であった。
愛妻を失った寡黙な老人が漂わせる控えめな寂寥感が、真夏の尾道の描写とともに心に染みたあのラストシーンが忘れられない。
本作は改作が加えられ、むしろ主役は「母」に置き換えられたと思う。母の優しさが次男と婚約者とのからみで浮き彫りにされ、誰しもホロリとさせらたのではないか。
内助の功の見本みたいな控えめな母がよく描かれているが、父親は前作とはかなり違い、好人物に描かれていない、ここが大きく異なるニュアンス。逆に笠智衆の存在の偉大さが浮き彫りになった皮肉な結果となったのでは。
変わりない夫婦愛は謳われているが。
時代も現代に置き換えられているが、広島の島生活は昔ながらの近所付き合いで、一人身になった父を地域が支えている筋書になっているが田舎も変わっており、他人の面倒など余りみてくれないのではなかろうか、少し無理があろう・・・原作の時は納得性があったものの。
東山千恵子と吉行和子、杉村春子と中島朋子、原節子と蒼井優、私には本作の方がキャスティング的には自然にみえたが・・・・。
親子別居で核家族が当たり前の都会暮らし、時代の変遷期を過ぎた今日、賞味期限切れのテーマであることが致命傷となり、あまり評判が良く無かったと思うが、力作ではあった。

No.33
故郷
1972/96分
山田洋次 監督・原作・脚本
井川比佐志、倍賞千恵子、渥美清、笠智衆、前田吟
「家族」「遥かなる山の呼び声」との3セットが民子三部作と呼ばれている。倍賞千恵子が同じ「民子」として主演を演じているから。
本作では切り出した石材を石船と呼ばれている木造運搬船で運ぶ、ボロ船の機関士を演じている。
夫婦二人だけの舟だから重い石材を手で移動したり、女性としてはかなりの重労働の場面があり、それを健気にこなすところが魅力になっていようが、本当はひ弱で、可愛すぎる倍賞さんには、イメージ上多少無理があると感じる人も居たと思う。
この作品の魅力は世にあまり知られていない「石船」という特殊な仕事を「主役」として選んだ事では無いか。木造船が埋め立て用の石材を当該場所に運んで海上投棄する際、クレーンが無いので船を傾け、荷崩れを起こさせて石をずり落とす。一歩間違えば転覆である。運搬の途中も喫水線がデッキと同じ高さなので、今にも沈みそうな状態で推進する。何気ない木造船だが復元力や浮力の構造計算に工夫があるのだろうが、この作業が驚異の風景で魅力満点である。
倉橋島と本土とは有名な「音戸の瀬戸」で隔てられているが、現在は橋が架かり「島」という感覚は薄れているが、当時は本土との地域格差が大きく、相当の田舎。
貧しいか故に地域住民は結束して近代化の波に抗しているが、次第に追い詰められて都会へ移住していく者の後が絶えない。
本作は古き良き島の生活への「挽歌」である。清く、貧しく、美しく、働けど働けど暮らしが成り立たなくなって行く、経済用語で言う所の「産業構造の変化」についていけない庶民の悲しみを、今は無き良き生活の憧憬とともに描いている。
でも石舟だけでなく、この現象は高度成長期以来、農業、近海漁業、炭鉱、繊維関係、造船・・・ いろいろな分野でそこに働く労働者に犠牲を強いたことは、あらためて記憶しておいても無駄ではないだろう、そのことが次世代に何を語っているかは本作では見えないが。
労働集約的な生産が、大量機械生産に置き換えられ、労働者の移動が全国の田舎の荒廃を招いたが、都会も又、人心が荒廃し犯罪の多発や公害など決して幸せになってはいない。
行き過ぎたものは修正される運命にある、元には戻れないが皆で多少貧乏を我慢し合いながら
も、昔の倉橋島の人達のように、自然と一体となった人間的な営みを少しでも目指していけないものだろうか、そんなことを考えさせてくれた作品だった。
瀬戸内海の綺麗な風景を期待していたが、敢えてそうはしなかったようだ、残念だが。
島の貧しい生活をよく観察して、前半は特に見応えのある展開。
ニュース映画のように、ドラマぽくしない作りがここでは成功か。

No.32
ソイレント・グリーン
1973/90米
リチャード・フライシャー 監督
チャールトン・ヘストン(ソーン)、エドワード・G・ロビンソン(ソル)、リー・ティラー=ヤング(シャール)
チャック・コナーズ(タブ)
1973年時点で2022年を舞台にした作品だが、「1982」とか「ブレード・ランナー」のように ある程度科学的に未来を予測して作られて、後日の検証に耐えうる内容の作品ではない。単なる怖いSF映画と言えよう。
怖いという理由はソイレント・グリーンは大豆から作った人工食料という触れ込みだが、実際には死者・・・。
それでも1973年という時代がお先真っ暗な展望しか描けなかった事が良く分かる。
これは前出の2映画と共通して言える。
もっと昔だったら、「猿の惑星」(1968)みたいに核戦争の恐怖で世界が滅ぶのが未来予測。
冷戦が安定し、核戦争の恐怖の次に登場したのが、「世界的な人口爆発」「環境破壊」であり
本作は2022年にそれによる末期症状を描いている。
環境破壊による「死の海」、「土壌死」で食料が枯渇し、一部の富裕層だけが人間らしい生活をしているが、庶民は全員ホームレスみたいな終末的世界。
そこへ正義の警察官がソイレント・グリーンという食品を製造している会社の実態を暴くという、お決まりの筋書。
だが、面白い場面もある。
自殺願望者のためのホームがあり、それは綺麗な国家的な施設で、ベートーベンの田園交響曲が流れる中、今は失われた緑に覆われた美しい地球の画像が映される部屋で、安楽死を迎えるくだりだ。
今はオランダにしか安楽死は認められていないが、この動きはあるいは今後拡がる可能性があるかも、かたちを変えてでも。
疑問:①石油が枯渇し無い限り世界的食料不足はないのではないか。20c初頭は世界人口は16億人だったが20c末には60億人に急増。産業革命が引き金と言われている。さらに石油の利用により農薬、肥料が安価に手に入り、石油による機械化大量生産、土木機械の発達による国土開発(開墾やダムなど)が食料増産の原因とみられる。
世界の人口は増加率が下がったという説も巷ではあるが、国連資料ではその兆候はみられない。今後の推計も千差万別で難問の一つらしいが、楽観できないことは肝に銘じておかねばならない。本作品の視点に間違いはない。
② 食料生産と人口は大まかに言って比例するので、食料が不足しているのに人口爆発というのはシナリオ上矛盾する
③何時の時代でも明るい未来は描けないものだが、実際には人も地球に生存する生物の一つで、自然界に順応して生き延びる本能を持っているので、破滅に一直線という行いはしないのではないか、そんな知恵が備わっているように思うが?
B級映画っぽいが豪華キャスト。

No.31
三度目の殺人
2017/125分
是枝裕和 監督・脚本
役所広司(三隅)、福山正治(重盛)、吉田剛太郎(摂津)
満島真之介(川島)、広瀬すず(咲江)、斎藤由貴(美津江
市川実日子(篠原)
役所広司、広瀬すず、さらに脇役陣の健闘など演劇人大健闘の力作である。
脚本は敢えて分かりにくく、観客に考えさせる、言わば投げかけスタイルとなっている。
そこで私なりの解釈を披露したい。
テーマ ① 真実とは何か ② 誰が裁くのか
三隅は2度の殺人を犯した。これは事実であるが、その動機(真実)は不明。彼は自分の心の中にある真実は世間には通用しなと思っている、真実は無力であることを経験から悟っている、だから決して語らず嘘証言ではぐらかせている。
善良な市民や親族が無慈悲に苦しみ、命を落とし、悪いやつらがのさばっている。神も仏も無い人生の裁き者に対する怒りが根底にあり、自分が「必殺仕置人」となって神の代わりをする。
しかしこれでは情状酌量で死刑にはなら無い、そこで金品を奪い、家を放火するなど、極悪人になる。でも如何なる場合も「人を殺せる人と殺せないひとの間に深い溝がある」と判事は信じて疑わない、本当のような気もするが違う様な気もする。
彼は神でも無いのに他人の命を奪った罪を死刑で贖罪したいと思っている。
いや初犯の前から厭世的であり、自殺願望があったのだろう。
初犯で死刑にならなかったのは、裁く人が真実をみつけたと認識した結果。そう認識しなかったら2度めの殺人は起きていないのだが、この判断が間違っていたかどうかは誰にも分から無い。
2度めの動機が咲江の登場で揺らぎ、情状酌量の余地が出てきたので、かれは一発逆転発想で、殺人そのものを否認し死刑が確定する。
結果として咲江の近親相関の被害も表ざたにならず、人を救ったことになる。
北海道留萌の元刑事がかれは「器」みたいな男と評する。
殺人を犯したという事実は容器そのものに例えられ動かしがたいものだが、その中身(動機)が何であるか皆目分から無かった と言うことでは無いか。
彼は真実を分から無いように嘘八百を並べ立てたから、動機がない空っぽな男と見えたものと思う。
器の中身に何を見るかが彼の理解につながる。重盛は三隅に自己犠牲をみたのだろう。
如何なる場合も殺人が認められるのか否か、法律では裁けない永遠のテーマである。
***
謎解き:①美津江は食品偽装の告発の口止め料として50万振り込んだ。ということは両人は示談したということだ。その時、美津江を脅し偽装隠ぺいの為の金を振り込めと言ったが、本当は三隅には保険金の為の計画的な嘱託殺人に見せる為の送金であった。
彼は週刊誌に保険金目当ての嘱託殺人だと語り報道され、法廷でもそれを主張した。
それは咲江の過去を晒さずにことを収めようとしたから。
そうすると、美津江が疵つき、本人も望まない減刑となる矛盾を解消するため、ちゃぶ台返しみたいな犯行否認で、嘘つきの確証を与え死刑を選んだ。
:②社長は三隅に何を言われて河原に行ったのだろう。偽装の相手と話し合う為、人目のつかない場所を指定したのだろう。それにしても河原は異様、警戒心が働らかなったのだろうか疑問は残るが。

No.30
あん
2015/113分
川瀬直美 監督
ドリアン助川 原作
樹木希林、永瀬正敏、内田伽羅、市原悦子
ハンセン病患者に対する世間の偏見がテーマ。
カンヌで「ある視点」に出品されたように重い題材に取り組んだ意気込みは大いに評価されよう。
あまり深刻にならないように、軽いタッチで流した感があるのか、その為印象が薄く私には少し期待外れ、評価の分かれるところではあるが。
谷深ければ山高し のことわざ通り 感情を沸点に持って行くには ハンセン病患者に対する
世間のえげつない差別をもっと克明に描く必要があったのではというのが私論。
徹底的に現場取材すればもっと、もっと きつい現実があったはずである。綺麗ごと過ぎないか。
樹木希林さんも体が悪かったのか、存在感がなく、ふわ~とした演技のように映った。
むしろ永瀬の方が良い。
千太郎(永瀬)が徳江(樹木)がハンセン病だと知って、飲んだくれただけで偏見を捨てる筋立てには無理がある。病に対する知識もないはずだから、逃げたいと思ったはずだ。
ここが重要、即ち一般人がハンセン病患者への偏見を捨てるにあたり、千太郎が例を示す必要があるのにそれを飛ばして、何時の間にか偏見を捨てている。
中学生のワカナは図書館で調べて、今日特効薬があり完治する病であること、伝染力の極めて弱い感染症であることなど勉強して知的な努力で乗り越えた。
若い人は偏見を捨てることは比較的簡単かもしれない、だが年寄は過去の記憶からそう簡単にいかないから感情的で、厄介だ。
厚生省のライ予防法廃止は1996年だ、遅きに失した。その背景は外観からくる一般人の強い差別意識を忖度したと言えなくもない。
役所でさえこの程度の認識だから、一般人は未だにもっと程度が悪いと思う。
これはライ患者だけの問題ではない、広く障害者に対する偏見も同根。
人間は生まれつき差別したがる性癖がある。
いじめっ子問題、貧富の差別、性別差別、学歴差別、身分差別・・・。
自分もその一人だと常に認識する事が大事ではないだろうか。
この作品で良かったのは、世間から隔離されることの辛さを理解する為に、服役経験のある千太郎を使ったことであろう。格子無き牢獄の辛さ、世間に出れる嬉しさ、一度失ったものでないと分から無い。
何かとやっかいな世間だが、世間なしでは生きられないのも性、そんな世間のあり難さも感じた作品だった。

No.29
ゲッタウエイ
1972/123分 米
サム・ペキンパー 監督
ウルター・ヒル 脚本(「48時間」)
クインシー・ジョーンズ 音楽
スティーヴ・マックィーン
アリ・マックグロー
ベン・ジョンソン
アル・レッティエリ
この作品は最初の5分位が、牢獄内の織機の絶えざる機械音に交じって、主人公の過去が細切れにフラッシュバックされ、仮釈放否決までひっぱり、そしてタイトルバックに入るという変わったオープニングになっている。
これが斬新に映るので、その後が大いに期待されるが、中身はそうでも無く、意外と定石通りだ。
金を持って逃げる話は、映画界のジャンルの一つで、ハラハラドキドキさせ、アクションもあるので、ヒット作が多い。本作も当たった。
問題は逃亡技術というか、逃亡ノウハウに新しいネタが要請されることだろう。
駅のコインロッカーの前に親切顔した人がおり、トランクを入れてあげましょうと手伝って、鍵をかけてあげ、違う鍵を手渡して、中身を盗む手口は実際の詐欺行為であるらしいが、私は初めてだったので、役立ち情報でもあった。
もしかしたら他作で使われていたのかもしれないが、そうだったらガックシだが。
汽車の中の犯人追跡、カーチェイス、ゴミ収集車での移動 は何回も他作で見ているので明らかなパクリ。又、強盗が亭主を縛り、その前で妻を犯しにも関わらず、妻はあっけらかんとして強盗に付いていくが、亭主は自殺するくだりも、西部劇で見たことがある。
詳しく検証すると、どちらが先か分から無いが、少なくともオリジナルは少ない作品と思う。
でも飽きさせずに最後まで一気に観させるので、娯楽作品としては一級品だろう。

No.28
君の膵臓を食べたい
2017/115分
月川 翔 監督
住野よる(♂) 原作 吉田智子 脚本
浜辺美波(桜良)、北村匠海、小栗旬(僕)、大友花恋(恭子)、矢本悠馬(ガム君)
2018年にアニメ映画にもなったヒット作品。
アニメは観ていないのでどちらの出来が良かったのかな?
若い監督、原作 なのでその目線で見る必要はある。
原作・シナリオ:他人と交わるのが苦手で、自分の世界に籠って、孤立している青年が主人公。最近の若者の典型だから共感を得たのかも。
多分作者自身を投影していると思われるが、作者自身自分で自分の魅力が良く分かっていないと思われる為、「僕」の人物像がくっきりしていない。その為桜良が何故「僕」を選んだのかがよく分から無い。要するに表面上魅力の無い男の内面の説明がないまま(一応あるが嘘っぽい)桜良にとって最良のパートナーとなるのが不自然。
エンディングが膵臓疾患で無く通り魔で命を落とすは意外性があって良いと思うが、何時死ぬかも知れないのが人生だから、その日その日を精一杯生きろ、というのは禅の教えなどで言いつくされていることで、改めて言葉で語るとB級映画に成り下がってしまうのでは。
(それとなく観客に感じ、考えさせるのが筋、はっきり言葉で言ってはいけない映画だから)
キャスティング:浜辺さんはネアカ過ぎるのでは。余命1年の女性だから明るくても何処かに影がある人が良いと思うが。
「僕」は記述のようにはっきりしないシナリオだから、役作りに苦労したと思う。
しかし12年後の小栗旬とイメージが違い過ぎる。小栗旬側に寄った方が。
ガム君のキャラクターは深刻事態の中の一服の清涼剤としてとても効いている、矢本悠馬の演技は評価できる。
気になった事ばかり書いたが、泣けるし、頭書に書いたようにスタッフは皆若い割には良くまとめたとは思う。特に若い人は評価するだろうという意味で目くじらを立てることもないのだが・・・。

No.27
サン・ルイ・レイの橋
2004/120分 西・英・仏
監督 マリー・マクガキアン
原作 ソートン・ワイルダー
ロバート・デニーロ、キャシー・ベイツ、ハーヴェオ・カイテル、F・マーレイ・エイブラハム
1714年スペイン統治下のペルーで起きた 大峡谷に懸けられたつり橋が崩落して5人の犠牲者が出たという事故を、目前に見た一神父がショックを受け、原因を調査したことが、大司教の逆鱗にふれ、宗教裁判を経て 火あぶりの刑に処せられたという話である。
従って、冒頭のセリフをちゃんと聞いてないと意味不明になる。
「この世は計画され、人生に型があるのか、その秘密が5人の突然の死に隠されているはず、
人は偶然に生きて、偶然に死ぬのか、生は定められ、死も定められているのか」
要するにカソリックでは人の生死は神が決めることになっているのに、その意思の証拠を探ったから罰ということ。6年間綿密に調査した神父は、確証が得られなかったので、単なる事故ではなかったのかと思い至った。5人とも極めて愛の人であったことが分かったからだ。
作品の胴体はこの5人の生前の生き様を追っているが、これがかなりお金のかかった衣装やセットで豪華、スペインに居るのが国王でペルーにいるのが副王で、これに貴族が従い、贅沢三昧をしていた、など当時のスペインの世界一の強大さを知る上では興味深いシーンが続く。
しかしその中には挿入の必要のない話が多く、又 親の子への偏愛 兄弟愛 名誉や金銭愛 誠実な愛 献身の愛 などいろいろな愛の典型を並列的に並べてだけで、収拾がつかないままクロージング(突然橋の崩壊)を迎えているのは残念。
神の存在の問題とか、愛とは何か、という大きな問題を真正面から扱うこと自体にそもそも無理があったのではないか、目論見がぼやけた映画になってしまった。
キャスティング:
デニーロはもともと権力者のイメージを持っている役者ではない。キャシーベイツは侯爵夫人というよりなり上がりの単なるデブ?
カイテルはいい、ペピータ演じた女性も清楚で印象深い。
チャップリンの娘も修道院長役で出てそれなり。

No.26
テス
1979/171分 英・仏
ロマン・ポランスキー 監督
トーマス・ハーディー 原作「ダーヴァヴィル家のテス」
ナターシャ・キンスキー(テス)、
ピーター・ファース(エンジェル)、
リー・ローソン、デヴィット・マーカム
これも文芸作品である。しかもアカデミーで撮影賞、衣装、美術監督、装置を獲得した171分の大作。
舞台はイングランド南西部のドーセット地方。緑の丘や森が広がる自然豊かな田舎。
この作品の価値の多くは、この美しい自然描写によっている。
落ち葉を踏んでの森の散歩、白い狩猟馬の列が水が流れるように緑の丘陵を疾走する、霧に覆われた古い教会、カーキ色の干し草、そして何より近くには、あの世界遺産「ストーン・ヘンジ」まである。
列柱の間から旭が昇るラストシーンは神秘的で見事という他無い。
ハーディーは他作品でもこの場所を好んで舞台に選んでいるそうだが当時(19世紀末)から人を惹きつける田舎だったのだろう。
***
ポランスキーは幼女趣味の変態男だが、そう主役のキンスキーという凄い美女もこの時まだ10代らしいが、監督の歯牙にかかっていたらしい、まあそれでも天は才能を確かに与えてしまった。
自然が美しくロマンティックに撮られている。
でもそれだけでは無い。それと相反するように厳しく汚い過酷な労働場面が極めてリアルに描写かれる。そう、もともとこの地区はとても貧しいのだ。
それが故にテスの人生を狂わせてしまったのだから。
村では妾は淫売と同じに見なされその子は洗礼を受けらず、死んでも葬儀が出来ない という下りがある。エンジェルも牧師の子であり、そのことに拘り、テスを捨ててブラジルに逃避する。この頃の田舎では教会を頂点とした村社会秩序が厳然とあり、それにはみ出した人間はそこでは生きていけない。何処でもある話だ。
貧しさ故に売られた女が帰還しても村に住めず、転々と出稼ぎ労働者として放浪していき、やっと見つけた幸せ・・・。
かなりメロドラマ調ではあるが決してそうではない。
貧困と偏見の中では、真実の愛は決して成就することは無く、それは周りを含めた悲劇の連鎖を呼ぶ他無い、という冷たい一つの現実を描いている とみる。
文芸作品だがこれは映画としても完成形。原作を読まなくても大丈夫。
退屈しないこと請け合い。

No.25
海の沈黙
この映画のdvdをwさんから借りたのだが、見始めてこれは岩波ホールで2010年に既に見ており、内容はよく覚えていたが題名を失念していたことに気付きました。wさんゴメンナサイ。
http://www.geocities.jp/teki_cyu/cinema.2010.html
上記をクリックして、No.35をお開き下さい。
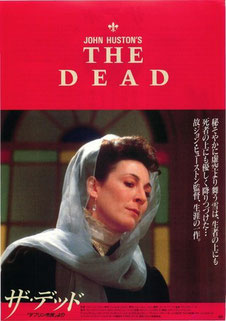
No.24
ザ・デッド
1987/83分 英・アイルランド・米
ジョン・ヒューストン 監督(遺作)
トニー・ヒューストン 脚色(監督息子)
ジェームス・ジョイス 原作(ダブリン市民/死せる人々)
ドナルド・マッキン/ガブリエル、アンジェリア・ヒューストン(監督娘)/グレイス<ガブリエルとグレイスは夫婦>
キャスリー・ディレーニー/ジュリア、ヘレナ・キャロル/ケイト<ジュリアとヘレナはホスト役の姉妹>
文芸作品である。さあ、原作を読まねば、例え難解なジョイスでも。
高松雄一訳「ダブリンの市民」集英社、15ある短編の内一番長い最後の1編「死者たち」。
これは「ユリシーズ」と違い一応読めるが、英文学専攻の学生が卒論に選ぶに相応しいような小説作法と深い内容を含んでいるのでかなり手強い。
だが、前半と終章の繋ぎは誰がみても不自然、二つの物語をくっつけた感じがするのだがどうだろう。
ヒューストンはドラマティックな終章に重きを置いて作ったとみる。その為前半を単に騒がしく作り終章は逆に静かな「語り」で締めくくって感動的を演出したのだろう。
原作も前半は群集劇風で色々な人物を並列的に描いて、誰が主人公だかはっきりさせずやや退屈、後半の演説あたりからガブリエルに光を当て、エンディングでさらにグレイスが鏡となってガブリエルの心を映す流れになって急に盛り上がっている。
映画化するにあたり、前半と後半のバランスに気を使ったことだろう。
ラスト: 生者、死者 この地上にあるもの全てに雪がしんしんと降り注ぎ隠していく。
「方丈記」にある無常観そのもの。
妻は若き頃 恋人を死なせてしまった。その自責の念は結婚後も終始心の大半を占めていた。にも拘らず、夫はそれを知らず良き夫を演じてきたという人生の空しさから敷衍して、今日の文明を作った死者達も、今生きている人の心を縛り続けているのではないかという仮定から「死者たち」という題名になったと考えるが、如何。
臼を回すため馬が円を描いて回る、その馬に乗って町に行った男は銅像の周りを馬がぐるぐる回るだけで前に進めないという事態に困ったという逸話が語られるのもそう。
ダブリン市民は死者が作った古きケルトの伝統や慣習(前半に登場するもてなしパーティ、ホストを称える歯の浮いたお礼の挨拶など)に浸って麻痺、腐っていくと言いたいのかもしれない。ジョイスはモダニズム作家と呼ばれている。
舞台は1904年、アイルランドは英国の植民地、国内は反英国か親英かで2分し、文化的にもケルト回帰と大陸文化導入など混乱していた。ガブリエルは愛国者アイヴァースに西のブリトン人と呼ばれる程保守派で、急進派と一線を画していたので彼女と諍いを起こしたほどだが、結局はパーティの挨拶は民族派を満足させる伝統に則った完璧なものだったという矛盾が、何処となく死者の勝利を暗示させている。だからグレイスの恋物語とリンクされるとも解釈されるが。
ジョイスは反民族派で独立の為に繰返し命を落とすは無意味との考えで、芸術は政治活動ではない純粋芸術の立場だったらしい。この作品は外国(トリエステ)で書かれたので自国を客観的に見られたのだろう。
ガブリエルはダンスをしても、ピアノを聞いても、歌を聞いても、食事の後の挨拶文が気になって仕方がない。他人と話をしたり、あ~だこ~だと推敲しているうちに、内容がころころ変わり、悩んだ果てがそれとは全く関係ない伝統的な褒め言葉だったという「意識の流れ」がこの映画ではメモを度々取りだすシーンで表現されている。
映画は20c最高の文学と言われるジョイスを意識してか、改作はなく原作にかなり忠実に作られている(化粧室で酔っ払いブラウンに髪を梳かせる、馭者が素人という設定は創作)。
ラストに「西に行く時が来た」というセリフがある。妻が死なせた昔の恋人マイケルの眠るゴールウエイ?いやそれは避けるだろう、お声が掛ったもっと西のアラン諸島かも知れない。
何故最後になって東の大陸自転車旅行を諦めて西の大西洋なのだろう、宗旨替えなのか、またまた疑問・・・。
もうこの辺りで、お手上げだ。
遺作を意識すれば、死者(ヒューストン)が後世に影響を与えることを目論む事になる。
まあそこまで邪推せず、「死」とは何かを考えた単純な取り上げと理解したい。
いやDeadは形容詞、Theがつけば死人という名詞。死生観と死人感はちがう。
生者と死人の境が曖昧になって行く、そんな香りが最後に立ち上る。

NO.23
万引き家族
2018/120分
是枝 裕和 監督
リリー・フランキー(浩)、安藤サクラ(信代)、
城 桧吏(祥太)、佐々木みゆ(じゅり)、松岡茉優(亜紀)
樹木希林(初枝)
この映画は出演者の関係性がブラインド仕掛けになっているので分かりにくい。そこで家族関係を整理しておこう。
少し推理もあるが。
①信代の元夫は家庭内暴力がひどく、殺されそうになった信代を救うため、浩はその夫を殺害してしまった。裁判では正当防衛が認められが死体遺棄の罪で5年の刑を受けた。出所して二人は内縁関係のまま初枝の家に転がり込んで現在も生活している。②初枝と信代の関係は明らかにされていないが、前科者でまともな職に就けない浩は信代と日暮里当たりで怪しい商売をしているところを、偶然に初枝に拾われ、まともな女になったと思われる。初枝は困った人を見て見ぬことのできぬ性格。
信代は初枝の娘として暮らすが全くの他人。
③亜紀は初枝の夫の先妻の子で、多分離婚後先妻と暮らしていたのだろう。その後父は初枝とも離婚し3番目の妻と暮らしていた。時々父に会いに行った亜紀はそこで金の無心に来ていた初枝を知った。
亜紀は母親が死んだか再婚したか何らかの理由で家を離れる決断をして、初枝の家に転がり込んだ。父も3番目の妻もそのことは知らない。義理の娘ではあるが、血の繋がりはない。
④祥太は松戸のパチンコ店の駐車場で車上荒らしをしていた浩に連れ去られ、育てられた。
祥太はまだ幼児だったと思われ、親の記憶が無いと言っているのに、浩をまだ父と呼べない設定になっているのはどうしてだろう。お前は捨て子と言っていたのかもしれない。子供を車に残し親がパチンコに夢中になり死亡するケースもある、単なる子供欲しさの誘拐ではない様な気もする。子供を放置したろくでもない親から救出したということも考えられるがこれは謎。
⑤じゅりも痣や火傷が絶えない家庭内暴力の犠牲者。食事もろくに与えられずに痩せており、外で寒さに震えているところを信代に救出され家族の一員となる。彼女は自分の意思で帰ら無い選択をした。
***
この作品はまず「そして父になる」の続編と考えられる。
少しニュアンスが異なるのは、狭い家で6人が重なるように寝て、万引きした品物で生活しているという貧しさが、リアリズム映画のように仮借なく撮られている是枝作品にしてはシビアーなタッチ。
家族って何? 血の繋がりだけなの、本当の親が子供にとって不幸の原因のような場合もあるよ、それを救ってやる他人は、誘拐犯なの?
既成社会では如何なる場合も誘拐は罪、貧しさ故に万引きせざるを得なくてもそれは犯罪、ましては子供に万引きを教えることなど許され無いが、何処か貧困層に対する社会構造の冷たさに対する暗黙の抗議の目線を感じる。
万引きする人間は子供を愛する資格が無いのだろうか。
自分は犯罪を犯してまで、全身全霊で子供を愛しているのだろうか、どこかで問われているみたいだ。
この血の繋がりの無い6人家族は助け合い、繋がっている。貧しいがそれを超えた何かがある。
でも柄本明演ずる駄菓子屋のお爺さんに祥太は言われる「じゅりにはさせるなよ」この優しさが伏線となり、すべてが明るみに出る。幸せは続かないのは予見十分だが。
祥太は大きくなり万引き家族では将来がないことを知って、追いかける浩に振り返ら無い。
もう大丈夫これから立派に厚生できるだろう。
一方、じゅりは親元に帰り、変わらず暴力を振るわれる、これが既成社会の一件落着だ。
初枝は自宅で息を引きとった。死亡届を出すと年金が止められるので、床下に埋葬する。
このテーマは既に映画化された。死体遺棄の罪が残り、今度は信江が刑に服す。
尚別件だが、浩の人物像がイマイチ不鮮明。
(殆ど罪の意識なく万引きしているようにみえたが?)
誰か教えてほしい。
信江の最後の演技が秀逸で評判を呼んでいる。
じゅりは今度は親元に帰る選択をする。
初枝も居なくなり、祥太も去り、信江もムショだからやむを得ないとしても、信江はじゅりが帰る決断をした事にショックを覚え、どんな場合も親に代われないという現実を認めてしまう。
この映画ではこれから幸せが期待できるのは祥太だけという暗い映画でもある。
でも他人の子供でもこんなに愛せるという事、どんなに貧しくても一ときの幸せを得られるという事を知った。
饒舌ではない細野晴臣の音楽も見逃せず、バイプレーヤーも一流揃い。力作である。
日本では万引き家族というのは変わった設定だが、インドとかジプシー世界では代々受け継がれている「職業」で奇異な存在ではない。
尚現在日本では、隠しカメラが設置され、専門の見張りもいるので、万引きは難しい、良い子はマネしないように。

No.22
緑の光線
1985/98分 仏
エリック・ロメール 監督
マリー・リヴィエール、リサ・エレディア、
ヴァンサン・ゴーティエ、ベアトリス・ロマン
ベネチアで金獅子賞を獲得した作品だが、多くの人が面白く無い思った珍しい映画。難解でもないので、ますます訳が分から無くなる。
この人は起承転結みたいな完成形を嫌って、日常の時間の流れを意味を持たせず淡々と描くという新しい映画作法を使い、時間(人生)をさらっと追っているのではないか。終始「日めくりカレンダー」を使い1週間位のの流れを描いている。
人生は何時もドラマチックに展開はしない、殆どが変わり映えのしない日常の些細出来事の繰返しと理解すれば、こんな作風も一理ある。
神経質で、自己意識が強く、心を開けない若い女性が、2か月のヴァカンスを過ごすにも誰も相手が居ず、みじめさが募る展開。男に声をかけられても、警戒心、不信感の方が強く逃げ出す、かといって孤独はいやという何処にも居そうな、ある意味矛盾した性格。
男にも気軽にナンパ出来る男とそれが出来ない男がいるように、女性も同じなのは日本も変わりがないが、2か月のヴァカンスがあるフランスではかなり深刻な問題で捨て置けない大問題。変わり者ではあるが悪い人間では無いので少し可哀想に描かれる。
この映画は「他人にあまり好かれ無い人」が他人とどう係っていけばいいのかという大問題を突き付けている。その気のある人は真剣に観るだろう。
他人に好かれるため、評価されるために四苦八苦して自分を見失い、結局幸せになれない人も多いので、自我を貫くか迎合するかの匙加減は「草枕」の悩みと同じで結論が出ない。だから本作はおとぎ話で終わらせている。
ヴェルヌの「緑の光線」:天気が良く空気が澄んだ日の日没には太陽が沈む瞬間に緑の光線が稀に現れる。これは科学的に正しいが、これを見たカップルはお互いの心を理解し合うことが出来るというのは単なるおとぎ話。
彼女はそれに出会った。
おとぎ話が現実になることも稀にあるのかもしれない。
否定は出来ないが、それを何時まで待てば良いのか、あまりにも長い時間の流れではある。

No.21
木と市長と文化会館/または7つの偶然
1992/111分 仏
エリック・ロメール 監督・脚本
パスカル・グレゴリー、ファブリス・ルキーニ
アリエル・ドンバール、ジェシカ・シュウイング
「海辺のポーリーヌ」「緑の光線」などで知られるフランスの
大監督72歳の時の作品。最後のヌーベルバーグ監督と呼ばれ
ているが、軽いタッチの作品が多い。
本作の題名が変わっているから見てみたいと思ったけど、内容的には映像というより、政治パンフレットの朗読のような内容で、会話だけで成り立っている、変わった映画。
でも脚本までロメール監督が書いているので、彼の社会問題意識の深さが垣間見れる貴重な作品でもある。
都市派か田舎派かの言い合いに始まり、近郊農村の都市化問題、農村の過疎化・高齢化、国内農業の失敗(灌漑による土壌悪化、単一栽培移行による価格下落時の問題)、輸入品による地場農業の衰退、地方再生と称する箱モノ公共投資・道路整備による環境破壊、未熟な緑の党、左右両党の無責任・・・、などに発展していく。
山積するこれらの問題はそっくり我が国の問題と置き換えてもおかしく無いほど似ている。
「木」は緑の党「市長」は社会党「文化会館建設」は国(共和党)の政策か。
本当かどうか疑問だが、地球の表面積の58%が道路で災害の9割が移動手段によるもの、というくだりがあり、要するにロメール先生は過度な流通発展が問題の根源みたいなことを暗示しているようだ。地産地消をせずニュージーランドから輸入した梨をフランス人が食べていることは確かにおかしいとは思うが。
消えゆく村の文化、価値観の均一化、も含め未来に対する絶望的な見方だが、これ以上の深堀はせず、10歳の政治家志望の女の子に未来を期待してさらりと終わる。
東京へも毎朝北海道の牛乳が運ばれている。それはつまるところ石油が安いから採算が取れるという事ではないか。小規模農家が激減していくのは、安価な肥料、農薬を大量に使い大量生産でコストカットする農家に負けるからだろう。
本作の中にも牧草育ちの牛は12年経ってもまだ元気だが、飼料で育てた牛は食べ過ぎで5年ぐらいで死ぬ とのシーンがあるが、石油漬けの農産物は不健康のような気がする。
結局石油が悪い? 石油を否定すれば昔の貧しさを肯定することになる。それは国民はノーだろう。いいことの裏には必ず悪いことがある・・・。
取りあえず皆で、国産で近場の作物を高くても買うように、生活習慣をつけることから始めべきなのは事実だろう。
気にいったセリフ:社会党は全ての責任を社会に押しつけ、自己責任を回避している。緑の党は環境だけで他問題との整合性に欠けている。共和党は選挙に勝つ事だけ。

No.20
さらば冬のかもめ
1973/104分 米
ハル・アッシュビー 監督
J・ニコルソン、R・クエイド、O・ヤング
さらっと観れば何が言いたいのか分から無いかも知れないが、
見た後、寂しい気持ちにさせられ心が落ち込んでから、その訳を考え直してみると、なるほどと納得させられるそんな深い作品である。
あらすじは たった40ドルを隊内の寄付金箱から盗もうとした(未遂)メドウズという18才の新兵水兵が理不尽にも8年という長い刑を言い渡される。その訳は隊長の奥さんが募金活動をしていたからという、個人的因縁によるものだった・・・・。
このほかにも海兵隊の暴力とか、海軍内の形式主義や理に合わない命令など、軍隊批判が沢山出てきて、軍隊生活は決してハッピーでないことが描かれる。
原題は The Last Detail(特派隊)、 日本題名の意味が良く分から無いが、上記メドウズという青年を二人の年配下士官が特派兵として、ノースカロライナ州のノーフォーク海軍基地から遥か北のメーン州のポートランドにある軍刑務所に移送するロード・ムービーである。
メドウスと言う青年は、他人に対して優しく、殴られても殴り返すことが出来ず、怒りさえも表現出来ない、極めて大人しい青年である。
ただくだらない物を盗んでしまう性癖だけが欠点ではあるが。
まだ18才、酒、女、喧嘩は勿論、友人との楽しい会話やスケート、ピクニックさえも知らない何か暗い過去を暗示させて物語は進行する。
5日間の移送期間中、J・ニコルソン演じる先輩水兵は、メドウスを故郷に立ち寄らせ、母親との最後の別れの機会を作ってやる。ところが、離婚して一人暮らしの母は留守。家の中を覗くと、部屋にゴミが散乱し、酒瓶が転がっている。アル中らしい。ここにも彼の帰るべき居場所はなさそうだ。彼は18才~26歳という貴重な年月をこれから獄中で海兵隊員に虐められながら過ごさなければなら無い。それまでの5日間をどう過ごすか。
二人の先輩水兵は彼の未経験だったことを、全てこの5日間で経験させ、この世への未練を無くそうと試みる。このハチャメチャぶりがコミカルに描かれ、おかしく、又悲しい。
ただそれだけの作品かと言えばそうではない。実はこの二人の先輩水兵も、それぞれ暗い過去を背負い、いやでいやで堪らない軍隊生活から抜け出せない状況にあり、一生を軍隊で暮らす他ないことを悟っている。
そう3人とも全く出口が無い人生なのだ。それは社会がそうさせたのか、単なる不運の連続なのか、本人の責任ではなさそうだ。
それでも人は生きて行かなければならない。八方ふさがりの3人が5日間をそれでも必死に生き、かけがえのない友情の架け橋を作るこの限定的な幸せが胸を打つ。
映画の中の話では無いように思える。人は多かれ少なかれ、八方塞がり的な状況に置かれており、その中で苦しみ歓びを見出すしか無い悲しい存在なのだろう。
この作品は45年前の作品で、当時ニューシネマの佳作として評価されたが、未だテーマが新しく、むしろ状況は過酷になっているのではないかと思えるその視点に感服させられる。
寒いアメリカ西海岸での移送で、オーバーもないので、手をこすり合わせてばかりいる。
ラストシーンで、凍り付いた誰も居ない公園でバーベキューをする場面がある。
冬のかもめ達はじっと我慢するだけ。飛び立とうとしたが失敗に終わる。
希望の無い結末だが、身に凍みた。
J・ニコルソンはカンヌで男優賞を得た。NYでは「日蓮正宗」が出てくる、お祈りすれば叶えられる宗教のように思われていたらしい 、効き目はなかったけど。

No.19
グランド・マスター
2013/123分 香港
ウオン・カーウァイ監督
トニー・レオン(イップマン)、チャン・ツィイー(ルオメイ)
チャン・チェン(カミソリ)、マックス・チャン(マーサン)
カンフー映画だから娯楽大作の範疇に入るのだろうが、技に関して言えば目を見張るようなものは出てこない(例えば黒澤の椿三十郎のラストシーンのような凄さ)ので、その意味では凡作であろう。そこで、カンフー映画で無かったら何かと問われれば ①イップマンとルオメイの恋愛映画 ②ルオメイと父親の親子関係 ③日中戦争から香港分離までの歴史俯瞰
要するに、主題が良く分から無い作品なのだが、何故か惹かれてしまう独特の風合いを持った作品となっている。
その要因は全体の流れが①唐詩にあるような時代と共に人生とは失い続ける旅みたいな無常観に支配されている事 ②映像が際立って美しいこと ③音楽も秀逸 ④カメラ展開のテンポが淡々とアダージョ などが考えられ 散文調(詩的)に作られたことが成功しているのだろう。これは多分にウオン監督の体内リズムから発しているものだろうから、この波長に合わない人は評価しないと思う。
チャン・イーモウもトニー・レオンもやはり泣かせる。大俳優だ。
ps:日本軍の侵略がかなり出てくるので、お気に召さない方もいると思うが、侵略された側からみる日本人観も知っていく必要があろう。
No.18
メトロポリス
1927/104分 米
フリッツ・ラング 監督
アルフレート・アーベル
ブレギュッテ・ヘルム
2016年に「死刑執行人もまた死す」(1943年)を見た。
これも反ナチ映画の傑作として高く評価されているがユダヤ人としては当然かな?と軽く受けとめ、評価4.00に止めていた。だが本作に出会い、考えの浅かったことに気付かされた。
本作はさらに16年前、原時点から言えば91年前の作品である(大正時代)。
当然無声映画であるが、その先見性、美的感性、奇抜な画面展開、などなど現代映画を未だに凌駕していると言っても過言ではない出来栄えである。
ラングと言う人は映画界のまさに巨人であったのだ。
① SF映画の先駆
・人間の代替労働者として、人型ロボットが製作され、人を扇動したりできる完璧な会話力
を持つ(ロボットのデザインは「スターウォーズ」の原型となったと言われている)
・当時まだ少なかった高層ビルが林立し、その谷間を複層高速道路が縦横に走り、タクシー
替わりだろうか小型飛行機が飛んでいる。(「ブレードランナー」でも同じシーンが使わ
れている)
・巨大な発電機関が街全体を動かしており、機関室の機械の歯車は「モダンタイムス」で
チャップリンにインスパイヤーを与えた。
② 社会主義
・労働者は搾取され資本家の奴隷となっていることに対する怒り。
貧しい労働者の子供達を初めて見た地上に住む資本家の息子にマリアが説明する「貴方の
兄弟達ですよ」(労働者は地下に住んでいる)
要するに人類愛を基本にした、平等社会を目指している。
しかし、ここでは調整役が登場し、お互いが思いやりを持つ事により和解する結論と
なっている。科学的社会主義ではない。
(余談だが16年後の「死刑執行人も死す」では自由は戦わなければ得られないと結論ず
けている)
・映画の冒頭で労働者の集団が時間交代で仕事場に向かうシーンがある。全員下を向いて
不気味な葬列のようである。このシーンはオーソン・ウエルズの「審判」でトリビュート
されていると思う。
③ 現在との相違点
・工場の機械制御は大きな時計のような操作盤を用いて人力で操作されている。現在は
電子制御まで進んでいる。
・ロボットを作るのに、フランケンシュタインもそうだが、必ず大きなフラスコのなかで薬
物が煮えたぎったりして、蒸気が充満している。言わば「化学反応」「有機反応」が人間
を再生できると信じていた。現在のロボットはすべて機械で動く工学的技術となっている
④ 余談
・4万人近いエキストラを使った大作だが、特殊撮影も見事。ミニチュアを使い鏡に映して
撮影したらしいが、今日見てもチャッチク無いのは凄い。
・大昔の映画なので完全版はない。世界の各地で発見された断片をつなぎ合わせたりして
いろいろなバージョンが存在するので矛盾点も出てくる。今回はtutayaのdvdをみたが
独裁者がロボットに労働者弾圧の口実を作る為、扇動してこいと命令する。
しかしロボットは機械を破壊するように動く。機会が止まれば労働者住宅は水没するだ
けでなく地上の資本家たちの生活も止まるので、そんなことを命令するはずはない。
ある資料によれば、資本家はロボットに労働者のマリア崇拝熱を止めさせるために派遣
したのだが、ロボット製作者は資本家と女のことで昔争ったことがあり、その意趣返し
でロボットに破壊を命じたとなっているらしい。
・無声映画なのにアフレコでモダンジャズが全編に流れている。少しヘン。
・20世紀初頭ドイツで台頭した印象派、自然派に対抗する芸術運動「表現主義」の作品と
との事である。表現主義とは私の理解では「感覚」ではなく「魂(こころの奥底)」を
表出させたものでシュール等抽象的な表現に繋がっている。
労働者の生活や地位は90年前と比べ改善されたのだろうか、ロボットの登場により人間の生活は今後どうなっていくのか、等々 人類のテーマは変わら無いことに驚ろかされる。

No.17
プレイス・イン・ザ・ハート
1984/112分 米
ロバート・ベイトン 監督
サリー・フィールド(本作でACD、GG主演女優賞)
ダニー・グローバー(有能な黒人労働者)
ジョン・マルコヴィチ(盲目の同居人)
エド・ハリス
1935年テキサス。夫を突然失った妻が歯を食い縛りながら、その後も逞しく生き抜いていく様を描いた作品。ハリケーン、KKK、痩せた土地など南部特有の問題、また大恐慌さめやらぬ貧しさ故の生活の厳しさを丹念に描き、それでも人種差別や夫婦間の愛憎を「愛」の力で超えていく姿が感動を呼ぶ。サリーはやり手ウーマンではなく、弱弱しい女性然でいながら、希望を失わず懸命の努力をしている姿を演じたからこそ評価されたのだろう。

No.16
ブレードランナー ファイナルカット
2007/117分 米
監督 リドリー・スコット
原作 フィリップ・k・ディック
音楽 ヴァンゲリス
ハリソン・フォード(デッガード)
ルトガー・ハウアー(バティー)
ショーン・ヤング(レイチェル)
1968原作、1982映画ブレードランナー、1992同ディレクターズカット版、2007同ファイナルカット版、2017ブレードランナー2045。4回映画化されている。
SF映画の代表作の一つ。原作から50年経っているから、当時の21世紀初めの予想を今日検証出来る面白さがある。
・環境悪化で地球は酸性雨が降り、空気が汚れ太陽光が届かない夜ばかり、人類の半分は宇宙へ移住し、遺伝子操作による人造人間(アンドロイド、映画ではレプリカントと呼んでいる)が奴隷として過酷な基地建設労働に使われている。
・空飛ぶ車がビル群の間を飛び交う
等が予想と違うが、チャイナタウンの屋台やショーなどは殆ど変化なく、武器も目新しいものは登場しておらず、殴り合いが主流、捜索活動も英雄的主人公の個人力に頼っており、全体構想としての新旧アンバランスは否めない。
我々今50年後の予想をしても、地球外への移住は困難であろうと思うが、クローン人間は技術的には既に可能だから現れているかもしれない。
私はこの映画を観て、Kazuo Ishiguro の「私を離さないで」の臓器提供のためのクローン人間の話を思い出し、悲しくなった。
生命の操作は差別を生み、悲劇につながる。
戦争以上に忌み嫌う対象であることを皆で確認しておきたい。

No.15
ラッキー
2017/88分 米 新宿シネマカリテ2018/4.12
ジョン・キャロル・リンチ 監督
ハリー・ディーン・スタントン(主人公の老人ラッキー)
デヴィッド・リンチ (リクガメを愛すハワード)
ロン・リヴィングストン(弁護士ボビー)
エド・ベグリー・jr(酒場の亭主)
トム・スケリット(元海兵隊員)
名作「パリ・テキサス」の主演俳優であるスタントンの遺作。
本作完成後すぐ91歳で亡くなった。
監督が彼をイメージして書き下ろした脚本。
友人である大監督デヴィッド・リンチも出演している。多分彼の掉尾を飾ってやろうという周りの配慮ではなかったか。それがそうなったのが怖い。
*****
この映画はインディーズ映画館である渋谷UPLINKで封切られ、現在は一般館であるシネマカリテで上映中であるが、次は同じ新宿の武蔵野館で上映の予定である。
映画の作りは西部劇風のコメディーだが、内容的には「死」を題材としている。
にも拘らず笑えて、泣けて、考えさせられる、極めて優れた作品であると思う。
特に年配者にお勧めである。
以下ネタバレとなるのでご注意
*****
スタントンは日本の笠智衆みたいに演技臭さが全く無く自然だから、まるで役柄なのか、本人そのものなのか区別がつかない。
この作品の役柄は独身で一人暮らしの90歳の老人。
ルーティン化した日々を淡々と送っている。
外に出ると、他人に決して媚びることが無い不愛想な男だが、毎日通っているカフェやバーやスーパーの馴染みには好かれている、多分嘘が無く、裏表が無いことがそうさせるのだろう。
そんな孤独な影を引きずるアウトサイダーが「死」を目前にして、一種の悟り?を開く語りがこの作品となっている。
元々彼は無神論者、クロスワードパズルの「リアリズム」を辞書で引く場面があるが、「物を重視」と書いてある。現実主義者で死を前にしても宗教に頼ろうとしない。
彼の人生観や世間の見方には悉く現代人として納得性がある、だから脚本が優れていることは間違い無い。
私には「禅」の匂いがした。
「生まれる前の自分は何だったのか」というセリフは漱石の「門」に出てきた円覚寺での問答だし、「無から生まれ無に帰る」とか、「全ての事物は常に変化し、亡びる」から財産なんて架空のモノだ、のくだりは「方丈記」を思い起こさせる。
そして、太平洋戦争の玉砕のタラワ島、沖縄、フィリピン、の様子も元海兵隊員に語らせているので。何処か日本を意識し、禅を勉強したのではと思わせる。
玉砕死を前にした少女の例えようもない美しさが忘れられない、多分仏教徒だから「死」を受け入れられるのではというセリフに「仏教的死生観」で死を迎えようとする意思も感じる。
人生はうたかたのようなもので、あっという間に過ぎ去ってしまう。見聞きしたものは全て今は無く自身も無に還元されていく。「無常観」が本当に理解されるのは死に近くなった人であろう。財産など架空のモノであの世に持って行けないと言っても、若いうちはお金は欲しいし、無ければ生きていけないのの現実。
目前に死がある人に大金は無意味だし、まだ元気な人はお金が欲しい。
後者の人はこの作品に感動しないだろう。でも言っておきたい、死は必ず前触れもなく襲ってくる。
***
舞台は「パリ・テキサス」と同じ砂漠地帯で、殺風景、風化した建物も、小さな町の佇まいも荒涼とした人生を感じさせぴったり。
それにこの音楽、マリアッチを謳う彼に涙する人も多いのでは。
ドラマ性が無く、舞台の転換もなく、何の見せ場も無い、カラカラの乾いた風合いながら、何故泣けてくるのだろう。
実際の自分の死を覚悟した人の最後の叫びが、作り物臭さ一掃し、人生の例えようの無い悲しさ、寂しさがこみ上げて止まないからだろう。名作と言って良い。

No.14
100歳の少年と12通の手紙
2009/105分 仏
エリック=エマニュエル・シュミット 監督・原作・脚本
ミシェル・ルグラン 音楽
ミシェル・ラロック(ローズ)、アミール(オスカー)
マックス・フォン・シドー(デュッセルドルフ医師)
アミラ・カサール(コメット婦長)
ミレーヌ・ドモンジョ(ローズの母)
白血病であと12日しか生きられない10歳の少年が、ある女性ボランティアとの交流を通じ、1日を10年のつもりで、必死で生きて行く病院内映画である。
12通とは一日1通神様に便りを書くことより、自己を見つめ直すということから来ている。
コミカル劇画も挿入され、面白おかしく作られているが、生きるとは何かという人間最大のテーマに足を掛けている、極めて真面目な作品である。
私は次のように考える。
12日しか生きられない人生、いずれは死ぬが当面は死ない人生、1日で花を付け種を作り枯れていく砂漠の植物。人生の長短とは何なのだろう。
作中「神様と人が違うのは、神は日々新しく生まれ、死んでいく、一日を作っていく事」というくだりがある。
人生に一日として同じ日は無い。刻々と過ぎゆく取り返せない時間が人生、あるのは流れではなく瞬間しかない。その時は前後の時間と関係なく絶対的な存在。過去に生きることは出来ないし、未来は予測でしかない。子規も小さな庭に宇宙を感じると言っている。1日の中にも長い人生が詰まっていると認識出来る。
長い時間、短い時間、そこに何を見出すことが出来るか、長い時間もぼんやり過ごせばあっという間に過ぎる。この作品では他人との交流の中に時間の意味を探っているが・・・。
何れにせよ絶対的な時間は存在しないのだろう。
明日は新しい過去にはなかった時間が生まれる。
そこに生きる。それが人生。
でも時間て何だろう、だから人生も、死も本当のところ分から無い。

No.13
マンチェスター バイ ザ シー
2016/137分 米
ケネス・ロナーガン 監督
マット・デイモン プロデューサー
ケイシー アフレック(リー)
ミシェル ウイリアムズ(同元妻ランディ)
カイル チャンドラー(友人ジョー)
グレッチェン モル(同妻)
ルーカス ヘッジス(リーの死んだ兄の子 成人役)
昨日観たのだが、深く心を動かされ、まだ普通ではない。
感動の故ではない、一人の男の出口の無い後悔、生き続けてはいけないという自責の重さにこちらが完全に負けているのだろう。
監督は元々脚本家だったらしいが(ギャング オブ NY)、フラッシュバックで過去を少しづつ暴きながら、現在の心情に迫る確かな脚本が際立っている。
それにケイシーの演技、逃れられない罪を背負い暗い影を落とし乍ら、世の中に背を向けて生きる男の寂寥感が観る者を切なくさせる。このような役どころを熟せるのはジェームス・ディーン以来の俳優かも知れない。
アメリカ東海岸北部はリトル・イングランドで建物も古風なものが多いが、寒くて決して住みやすい所では無いと思う。マンチェスターも港と言い、街といい どこか荒涼としてリーの心情を表象している。この舞台設定もいいし、敢えて赤とか緑とかの明るい色彩は使われていないのもさすが。
火事の場面で流れる音楽はアルビノーニのアダージョ、多用される曲だが、本作では際立った効果をあげている。
要するに、脚本、配役、撮影、音楽 皆揃っているレベルの高い作品だ。
ネタバレが怖いので、この辺で終わりにするが是非見て欲しい良作としてお勧めする。

No.12
この世界の片隅に
2016/129分 日 アニメ
片淵須直 監督 原作 こうの史代
音楽 コトリンゴ
声優 すず/のん
カンヌからアニメが分離されたのがアヌシー国際アニメ映画祭
で、この長編部門で審査員賞を獲得したのを始め、日本アカデミー賞最優秀作品賞、キネマ旬報ベスト10の第1位、又全米で公開されるなど国内外で評価された話題作で、興行的にも成功した。
原作は こうの史代さんのコミック。広島出身漫画家で既に、「夕凪の街 桜の国」は佐々部清監督により2007年に映画化され大好評だった。
両作とも戦争、原爆が題材でやさしい女性目線が際立った作品。
本作は作画、音楽、声優 どれもすばらしいが、特に食糧難の時の食事の工夫に感心させられたり、海軍の町呉の地理や空襲の回数などよく調査されているのにも驚いた。
映画、原作共に決して簡便に作られたものではない力作といえる。
内容的には、小姑の意地悪とか極度の物資不足とか手を失った喪失感とかの苦しい状況が余りにもさらりと描かれている為、作りものの悲劇感を軽くではあるが禁じえなかった。
主人公スズは喧嘩したり、怒鳴ったり、泣いたりし、我儘も言ったりしたはずだが、いつも笑顔を絶やさないマリア様然としていため、人物像の焦点がぼやけてしまったという事。
戦争はリアリズムそのものだから、もっと人間の醜い姿もさらすべきではないかと思ったが、逆にシリアスな題材だから敢えてポエティックにメルヘンとして迫ったと監督は言うかもしれない。確かに戦争の悲劇は語り尽くされているから、今更同じスタンスでは振り向いてはくれまいが。しかしこれだけは言える、極限状態を生き延びるのは善悪を超えた生への執念と言うか、強さが求められると思う、マリア様では餓死するだろう。
本作品は一言でいえば「スズ」の半生を描くことにより、どんな境遇でもくじけず工夫を重ね乗り越えていく一庶民の生活賄いに光を当て、女性を再評価したという趣旨だろう。
その意味では、多くの年配者の母親像とダブって、母の苦労をあらためて偲ぶことになろう。
反戦は誰しも望むところだが、知らないうちに戦争に向かっており気がついた時はもう遅かったという歴史を振り返り、現在を点検し直したいものだ。

No.11
ブルジョワジーの秘かな愉しみ
1972/102分 仏
ルイス・ブニュエル 監督 カリエールと共同脚本
ジャン=ピエール・カッセル、デルフィーヌ・セイリング
フェルディナンド・レイ、ポール・フランクール
左のポスターから愉しみとはセックスのことでは無いかと思えば
大間違い。食事会の事である。
本作と下記No.10の「銀河」と「自由への幻想」この3部作は同類項とされている。
ブラック・ユーモアが基本線で、自由奔放な表現方法をとり、筋書とか因果関係とか訴たい事とは無縁の風変りな作品群である。
彼は人生とか人間を泡のような捉えどころのない不確かなものと考えているらしく、その為全てに対し「不信」を抱いているように見える。
映画の中で7人が食卓に座って食べ始めようとすると、後ろのカーテンが突如開いてそこには
舞台を見つめている観客が大勢いる、という下りは19cスペインのある戯曲に登場するらしいが、こんな奇想天外なアイデアを無秩序にかき集めてみて、この偶然性が観る者に何かインスピレーションを与えられないだろうかという実験的な遊びが映画製作だったのではないかという気もしてくる。
前後の関連性は皆無。だから100人居れば100通りの解釈が可能、作品評価も大揺れ。
この作品にも夢が多く使われている。死人が蘇って話をしたりするのは「銀河」と同じだが、本作の方が夢は夢として現実とは異なっているという線がはっきりさせているので、より自然で分かりやすい。それにしても「夢語り人」というアイデアは相当面白い。
余り意味を考えることもないが、外交官とその家族計6人(ブルジョワジー)の愉しみは食事会で、食事の枕詞的シーンとして必ず田舎道をテクテク6人で歩いていくのだが、必ず邪魔が入るとか、日を間違えるとか、奥に死人がいて止めるとか、決して食べることが出来ない。
食事だけでなくsexも邪魔が入り成就しない。この映画は目的が達成され無い連続となっている。
外交官特権を利用して麻薬で稼いでいる悪者達なのだが、それで楽をして人生が楽しいかと言えばそうではなく、絶えず怯えながら生きているので、夜の夢は悪夢ばかり。
満足な食事も出来ず、テロに狙われ、警察の目を絶えず気にしてい彼らが惨めかというとそうではないらしい、淡々としている。
それが滑稽でむしろ憎めないと思えるのは何故だろうか。
人が生きるということはそんなものだという達観的な香りもしてくる。
「銀河」はホームレスが主人公、本作はブルジョワジー、どちらも幸福でも不幸でもない。
ただ日常が繰り返されるだけで、大差ないか・・・。

No.10
銀河
1968/102分 仏・伊
ルイス・ブニュエル 監督 カリエールと共同脚本
ポール・フランクール、ローラン・テルジェフ、
アラン・キュニー
ブニュエルと言えばW・アレンの「ミッドナイト イン パリ」を思い浮かべるひとも多いと思う。
「Rolling Twentys」 と呼ばれる1920年代の爛熟したパリ。
ポリドールというカフェでヘミングウエイ、フィッツジェラルド、ピカソ、ダリなどに交じってブニュエルも登場する。
アレンはブニュエルとその後交流もあったので、彼へのオマージュのつもりだったろうが、年代的には大御所の芸術家より少し若い(1900~1983)。
一般的にはシュールリアリスムの人と呼ばれている。現実に囚われない、内面的な感性で表現しようとした。場所や時間に縛られず、目の前のものと妄想が同時に進行したり、現在と過去が交錯する。フロイドの意識下の概念、夢の世界 と明らかな関連性があるようだ。
現在の映画では、時間や場所が交錯して進行するのは珍しくないので、彼には先見性があったというべきだろう。
主客転倒ではあるが連続して意表を突くためには、キリストやマリアの奇跡の数々が使える宗教という題材は確かに面白い題材で、中でも突如修道女が掌に釘を打つ場面展開には誰しも驚愕させられるだろう。
このように奇抜な面白さ、理不尽さがまかり通るある種の滑稽さなど面白さはあるが、
でも正直に言えば、ダリやピカソ(彼は色々変遷したが刺激の発端はシュール)の絵に感動しないのと同じで、本作も感動はしなかった。
それは基本的には抽象絵画や現代音楽と同じに、「感動を届ける」より「より新しい表現方法を求めて」に力点が置かれているからではないだろうか。
その意味ではW・アレンに作風が引き継がれているのではないか。
本作は殆どが宗教論争、神学論争で終始する。無神論に組するのであればそんなに目くじらを立てなくても良いとおもうが、幼少時からイエズス教会に浸っていたので、まだ未練があるのだろうか。ロードムービーの主な舞台はフランスだがスペインという風土を強く感じてしまうのはそのせいかも知れない。
ps:コンポステーラは俗説では星の広場という意味らしい。9cに星に導かれて修道士が聖ヤコブの墓を発見し教会を建てたという故事から来ている。サンチャゴ・コンポステーラ教会には今でも毎年50万人というカソリック信者がヨーロッパ各地から巡礼の旅をしている。
原題はフランス語 la vois lactee 、英語でいえMilky way 日本語では銀河。
導かれたのが銀河だったのか流れ星だったのかは詮索不要、故事だから。

No.9
チョコレートドーナツ
2012/97分 米
トラビス・ファイン 監督
アラン・カミング(ルディー)
ギャレット・ディラハント(ポール)
(あらすじ)
ルディーとポールは同性カップルである。マルコはダウン症の少年。マルコの母は麻薬中毒で収監され孤児となった処を隣人のルディーに助けられる。
米国では保護者は健全な家庭生活者でなければいけないと思っている人が司法関係者でさえ普通にいる。ゲイ夫婦ではその資格が無いとされ裁判沙汰になるが結論として負ける。
そして悲劇が訪れる。
(経済的弱者とは)
資本主義社会では競争原理で動いているから、必ず敗者がでる。
勝者が権力を握り搾取するので敗者は貧困に陥り、教育の機会も得られずますます貧困になっていく。富の集中と貧困の再生産これが構図である。
でも、大衆の貧困度が限度を超すと犯罪が増加し、安心して暮らせる基盤が失われるため、
生産性も落ちてくる。そこで勝者は敗者の不満が暴発しない程度に救いの手を差し伸べる。
これが福祉政策。いわば限度付きの弱者救済である。
(道義上の弱者)
例えばゲイ。単に人に毛嫌いされるだけでなく職場からも締め出され困窮する。二重苦。
例えばダウン症の子。保護者がいない場合、善意のボランティアが名乗り出てもゲイの場合、行政は隔離する。要するに、障害者やゲイは世の中に居て欲しく無いという本音がでる。
(弱者切り捨てか救済か)
でもここで良く考えてみよう。ゲイは自ら好んでゲイになった訳ではない。そのような遺伝的要素をもってこの世に生まれただけで本人に責任はない。ダウン症も同じだ、本人には何の落ち度も責任もない。親に責任があるかといえば、親も選んで産んだ訳ではない。人類の進化の過程で偶然に他人に疎まれる存在を担っただけで無実な被害者である。
経済的敗者にしても、どんなに努力しても競争社会では敗者を生むのだから、自分が勝者になれば誰かが敗者になるだけの話で、自動的に社会が生み出す必然で本人の責任ではなかろう。
(自由主義か社会民主主義か、あるは米国型がEU型か)
そう単純では無いが、「弱者切り捨てか弱者救済か」の選択は個人によって様々。小さなサークルでさえ意見が衝突する。競争が進歩を生むのも事実だし、福祉の行き過ぎは財政破綻をもたらすのも事実だから、意見が分かれる。
でも私は思う、障害児を観る目を「本人の責任ではない」という視点から、もっと温かく出来ないだろうか と。これぐらい誰にも出来るはずだ。
映画興行用の問題点:
本作は問題提起という点での存在価値が高い。だが宣伝文句がセコイ。実話とうたっているが結末が事実と正反対らしい。幸せいっぱいな愛の映画みたいな動画配信だが、これも嘘。
日本側の興行主は映画フアンを馬鹿にしている。まともな作品だけに問題だ。
原題 eny day now 誰か訳して!

No.8
バーディ
1984/120分 米
アラン・パーカー 監督 ウイリアム・ワートン 原作
マシュー・モディーン(バーディ)、
ニコラス・ケイジ(アル)
原題のBIRDYという言葉は鳥、小鳥を指す幼児語らしい。
鳥が異常に好きなだけで、他のことはまるっきし疎いから、からかって幼児語を名前としたのだろう。
でも、これが本作の本旨になっている。
社会は全て狂っているとの認識。遊びとしての生徒同士のsex、親の押しつけと暴力、極め付きはベトナム戦争とPTSD治療施設。だから彼は鳥に埋没し、狂人のふりをして、現実逃避する。
これはベトナム戦争で心を病んだ若者の悲劇ととられがちだが、決してそれだけではない。
純真な青年からすれば、生きにくい世間なのだろう。
現実に折り合いをつけて生きている人間の方が狂人。
だから本作は「ドンキホーテ」の現代版と言える。
そう思ってあらためて身の周りを見てみると、株の乱高下に日々肝をひやしている人たち、広告だらけのTVをぼ~とみている老人、ゲームに夢中な若者、行列してアイスクリームなどを買う人達、売れ残った食材を毎日廃棄する業者、などなど 狂人世界の現象以外の何物でも無いように見えてくる。
狂人にならず、まともであることは可能なのだろうか、考えさせられるた。
ニコラス・ケイジ 顔半分包帯姿で抜群の演技をしている。

No.7
ナチュラル
1984/138分 米
バリー・ロビンソン 監督(レインマン)
ロバート・レッドフォード、グレン・クローズ、
ロバート・デュバル、キム・ベイジンガー
私はスポーツ物が好きだ。
万事休すみたいな状況から一発逆転の大ドラマが起こっても不思議でないのがミソ。
現実の試合でも信じられないドラマが生まれるが、それはかなり珍しい。ところが映画の世界では必ずそれが起こるから興奮する。
本作はナチュラル(天才)少年がカブスの入団試験に行く途中ピストルで撃たれるという事故に遭い、野球を断念するという意外な始まり方をするので、これはサスペンスかなと思っていると、中年になって復帰し大活躍するというやはり一発逆転のスポーツ・シナリオだった。
この映画は欠点をあげればキリがない。殺人犯(未遂)の動機不明、復帰するまで16年間の空白が謎、レッドフォードが選手にしては年をとり過ぎている、MLBの草創期の話とは言え守備や走塁が草野球レベルだからゲームとしての臨場感が乏しい、伏線から結末が読めるなどなど。
以上欠点はあるが、病院から抜け出して血を出しながら逆転ホームランを打つという、ありふれた「どん臭さ」がいい。「明日のジョー」ならホームベースを踏んだところで息絶える ところだろうが、映画は結末を示さず終わる。
息子が父親に初めて対面したのは、息絶えたホームベースの上だった・・・
こんな結末を想像するのも楽しい。

No.6
黄金のアデーレ 名画の帰還
2015/109分 米、英
サイモン・カーティス 監督
ヘレン・ミレン(アデーレの姪マリア)、ライアン・レイノルズ(弁護士シェーンベルグ)、ケイティー・ホームズ(同妻)、ダニエルブリエール(オーストリアの記者)
左の写真の中の絵は1億3,500万ドルという史上最高値でマリアからローダー氏(エスティー・ローダー 世界的化粧品会社)
に売却され、現在NYのノイエ・ガレリエ美術館に展示されている。本作はこの絵の所有権をめぐる国家を巻き込んだ長期裁判闘争の話である。実話。
正式な絵の名前は「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 Ⅰ」「接吻」と並び賞されるクリムトの代表作である。芸術家のパトロンであったアデーレ夫婦がクリムトに彼女の肖像画を2枚書かせたうちの一枚。(2枚目も高額でローダーが買い取った)
何か金屏風に貼り絵をしたような日本の琳派風の絵で、絵と言うよりは金粉を使った豪華な工芸品を思わせるが、海外ではそれが独創的だと高く評価されているのだろう、少なくとも私には装飾的で心が震えるような絵ではない、そう見える。
原告のマリアはオーストリア亡命米国人、マリアの両親とアディーレ夫婦は兄弟同士、要するに二つの家族同士で二つのカップルが出来た。従ってマリアはアディーレの姪。
兄夫婦には子供が居なかったので、マリア姉妹はアデーレ夫婦に可愛がられて育った。絵でアディーレがしている豪華な首輪はマリアが結婚した際彼女に譲られた程、家族同然だったらしい(その後首輪はナチスに没収されたが)。
アディーレは絵の通りに美人だったが腺病質で早世し、遺言で絵をウイーンのヴェルベデーレ美術館に寄贈との事だったが、夫がその絵は俺の物(金を出したからの理由か?)だと言って約束は履行され無かった。そしてオーストリアにナチスが進攻してきて、国外逃亡している間、居間にあったその絵はそっくりナチスが持って行った。彼は遺言で姪達にその絵を譲ると書いて他界した。これが後の紛争の種となった。
ドイツが負け、戦後それが国に返還され国有となった。被告である「国」はアディーレの遺言の正当性を根拠に、原告のマリアは叔父の遺言を根拠に法廷闘争に入る。
結果としてマリアが勝ったが(アデーレの遺言はナチの進攻前で、もしその後であったら国に寄付はしなかったであろうと、判断されるので私は妥当と考える)、それでも絵はやはり母国で保管すべき(ベルべデーレで接吻と並んで)ではないか、いや母国に対する個人的恨みを尊重して米国に渡るべきだとか、世間の意見が分かれるところではある。
この話はユダヤ人特有の問題でもある。この家族親族一家、弁護士(著名な音楽家シェーンベルグの孫)、ローダー氏 皆ユダヤ人である。オーストリアはナチ進攻に殆ど抵抗せず、民衆は一緒になってユダヤ人を追い詰めた。ユダヤ人にとって「母国に裏切られた」という事実は簡単には消えない。
裏切りの国に財産を託したくない、かと言って米国という「国」が安住の地である保証は無い。彼女は高齢である、選択肢は少ない、選んだのはユダヤ人社会に委ねる事。
ディアスポラ・・・流浪の民は国を持たないで2千年生きてきた、ヤハウエの戒律「隣人(ユダヤ人)を愛せ、敵(非ユダヤ人)を憎め」という選民思想が表象した結果と理解出来ないか。
ユダヤ教的な考えの他に、お金に拘り過ぎたのも特徴的な女性。
絵の保管は委託ではなく売却でなされたからだ。
弁護士が私費を投じて生活が苦しかったこともあろうが、それであれは少額の謝礼金で済むはず、なのに370億円以上(クリムトの他作も含め)の莫大な金を手にした。その必要が90歳の婦人にあったとは思えない。殆ど病的な守銭奴。各方面に寄付はしたが、怖い話である。
クリムトは放蕩三昧だったらしいが、純愛っぽい作風で女性にフアンが多いのも不思議な現象だ。その絵がたまたま叔母の家にあっただけで、膨大な金が手に入る世の中の仕組みも又、
不思議。
絵の相場といい壮大なキチガイ狂想曲。
この絵が余計くだらなく見えてきた。

No.5
アンドレイ・ルブリョフ ☆4.0
1971/182分(完全版1966/205分)
ソ連 dvd
アンドレイ・タルコフスキー 監督
A・コンチャロスキー 共同脚本
アナトリー・ソロニーツイン(イコン画家アンドレイ)
イワン・ラピコフ(僧侶仲間キリール)
ニコライ・ブルリャーエフ(イコン画家フェオファン)
ニコライ・グリンコ(アンドレイの助手ダニール)
ニコライ・セルゲーエフ(鐘鋳物師ボリースカ)
15cロシア大公国を舞台にした、最高のイコン画家アンドレイ・ルブリョフの生涯を描いた超大作。観る者を混乱させるべく作ったとしか思えない程筋書が追えないので(カットが多すぎたかも?)まず下記の時系列を頭に入れておく事と、3か所の修道院という場所的な要素を頭に入れて観ることをお勧めする。
全体構成
第1部
1.プロローグ(気球で空高く神に近づこうとしたが失敗 の意味か、意味不明)
2.1400年/旅芸人(民衆に人権なんてない、僧侶の裏切り、傲慢な官憲)
3.1405年/(画家フェオファン・グレクの登場、民衆は無知だから自業自得)
4.1406年/アンドレイの苦悩(フォーファンとの宗教論争)
5.1408年/祭日(異教徒の風習が奇異に描かれる、しょうろう流し?東洋系だろうか)
6.最後の審判(筆が進まない、佯女が救うらしい説明が無いが)
第2部
7.1408年襲来(ウラジーミルはまだタタールの支配下ではなかったらしい)
8.1412年沈黙(殺人の罪への贖罪で筆を折り、言葉を封印)
9.1423年鐘(民衆への献身、自己の存在)
10.エピローグ(この場面だけカラー)
頭が混乱する理由のひとつに、舞台となる修道院が3か所に分散していることもある。
最初は ザゴルスクのトローイッツェ修道院(上記2はモスクワのアンドロニコフへの移動途中の逸話)、次がアンドロニコフ修道院(3はこの修道院時代の話)、最後がウラジーミルのウスペンスキー大聖堂(4以降)。
本作はA・ルブリョフという敬虔な僧侶・画家の一生を描いた単なる伝記で無く、その時代の宗教観、僧侶や百姓などの民衆の生活は如何なものだったろう、という歴史探索に重きが置かれているのが特徴。
歴史検証:タタールのくびき(過酷な税金)という言葉がロシアにはある。
残虐な蒙古人といイメージが定着しており、それに勇敢に立ち向かった英雄たちの活躍が、民話化、オペラ化され今日まで来た。
でも、蒙古による帝国支配の実態はどうだったのだろう。極めて少ない蒙古人だけで大帝国が維持されていたとも思えないし、帝国とは名ばかりで地方自治は大幅に現地人に委譲した、共存共栄の融和体だった可能性も考えられる。
本作では、モスクワ公国の弟がタタールと結託し、兄の町を焼き払う場面がある。悪=蒙古、
善=ロシア という単純図式とはなっていない(ロシア人がロシア人を殺す)。
モスクワは1237年には蒙古軍で灰燼に帰してから約250年間キプチャク・カン国の支配下にあった。(5)の夜の祭では異教徒が登場するが、翌朝公国の兵隊により残党狩りが行われているから、これはタタールでもなく、ロシア人でもない人種だろう。
要するに、末端まで管理の行き届いた地域ではまだなく、未開地と思われる。
それにしては、僧侶をたくさん抱える立派な修道院があるのも不思議だ(もっとも僧院が農奴を売り飛ばしていたり、商売したり かなり腐敗していたが)
何れにしても、モスクワは極寒の地、ボロを重ねた服を身にまとい、凍てついた地を百姓が這いずり回っている。作物もあまり取れず、飢饉が起きて僧侶でさえ、腐ったリンゴを食べる場面もある。佯女が腐った肉をさらう場面もある。廃村が続く、日本の東北地方もかつてはそうだったように、食べ物が無く死んでいく人々。
全編に流れるロシアの大地の過酷さ(ほとんどが晴天ではなく、氷、雪、雨ばかりのシーン)
から、ロシア人の凄さを今日尚再発見できる様な気がする。
モスクワ公国のタタールとの関係やその過酷な治制など、ことごと左様に、今となっては歴史の解釈も難しい。検閲に5年間もかかっているので改定もあったろうから、事実を伝えた歴史作品とは言えないかも知れない。
本作はアンドレイを主人公に描いているが、キリールの方が良く描かれていて分かりやすい。
公国の兵隊に密告して旅芸人を10年間も牢に入れるとか、無視されたことに腹を立てて出奔したり、最後は腹が減ってアンドロニコフ修道院に戻るとか、アンドレイより人間的に描かれている。そして最後はアンドレイへの嫉妬心を告白し、才能ある人は後世の人の為に絵を描き続けるべきと諭し実現させ、その為事実今日まだその絵は残っている。
この映画はセリフが多く饒舌、静謐な後年の作品とは又一線を画す。
映像的には、ベルイマンを思わせるモノクロで陰影が深いのが特徴で、戦闘場面や大型鋳造場面など相当のお金も掛けている。国家予算を出した方も大したものだ。
エンディングだけカラーになり、「民衆に奉仕」に目覚め再び筆をとった力作がパンされる。
信仰とは何か、悩みや苦難を超えて会得した一僧侶の魂が半分剥げかけた壁に張り付いている。
信仰に生きることと絵を描くことの関係、支配層と僧侶の関係、民衆と僧侶との関係、僧侶と生活の関係、信仰スタイルの多様化、暴力と宗教、いろいろな論点が提起され、最後は宗教組織も僧侶も迷える民衆の為にあってこそみたいな常識論で終わっている。
難解と言うより分かりにくい作りが気になった。

No.4
ローラーとバイオリン ☆3.5
1960/46分 露 dvd
アンドレ・タルコフスキー 監督
少年サーシャ:イーゴリ・フォムチェンコ
ローラー運転手セルゲイ:ウラジーミル・ザマンスキー
タルコフスキーの映画大学卒業制作映画、即ち処女作だがNYの国際学生映画コンクールで一等賞を取った。28歳の時の作品。
46分という短編だが(短編にしては長い)、初めて世間の評価を得た事により、進むべき道の確信を持てたと思われる重要な作品。
これはごく普通の作品で、少年と青年の心の交流が描かれているだけなので、後の感受性の強い映像へどのように変化していったのか、興味をそそられた(鏡とか、夢想とか その萌芽は少し見られるが)。
サーシャは彼の幼少期だと思う。仲間から虐められ、喧嘩も弱く成績(バイオリン)も芳しく無かった。彼の劣等感を救ったのは道路工事で使う重い鉄のローラーの運転手セルゲイ、子供にとって運転させてくれるなんて最高の嬉しさだったろうし、きっとこれは長じても忘れられない思い出となっていたのであろう。
人は最初は自己の体験を題材にするものだから。
社会主義ソビエトでもバイオリンを習うような家庭と労働者の階級差別があったのだろうか、母はセルゲイと映画に行く約束だったサーシャを家から出さないで、封印した。
意識だけが階段を駆け下り彼を追うが、別離の感情、悲しいエンディング。
タルコフスキーは大器晩成のような気がする、その後の変化、進歩の幅が大きいから。
あるいは、もともと感受性が強い人間がその発露手段を後日獲得しただけかも知れないが。
ビルの解体作業場面がある、大きな鉄球の振り子がコンクリートを叩き壊す。
この衝撃音が重い、この人は音声にも相当拘っている。
市川崑監督の東京オリンピック(1965)で同じ場面があったのを思い出したが。
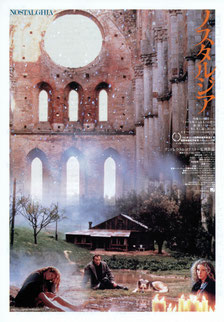
No.3
ノスタルジア ☆4.5
1983/126 伊・露 catv
アンドレイ・タルコフスキー 監督・脚本
オレグ・ヤンコフスキー(露詩人 アンドレイ)
ドミッツイアーナ・ジョルダーノ(伊通訳エウジニア)
エルランド・ヨセフソン(狂人 ドメニコ)
ラリア・ポカルド(同 妻)
タルコフスキーは映画完成後亡命、3年後に癌でパリで死す。
53歳、遺作は86年の「サクリファイス」。エンドロールに「母の思い出に捧ぐ」との献辞がある。
「鏡」(当ページ2016年版No.4参照)は自伝的作品なので、それによると父は幼い頃家を出て
母親に育てられたが、母との関係はあまり良く無かったようなので、献辞の意味は何処にあるのだろうか。
イタリアで制作されたあと、もう故郷に帰ら無かった訳だから、ロシアへのノスタルジーが母の思いでと一緒になって感傷的になってゐたのかも知れない。
この作品は特に現代社会に対する漠然とした深い絶望感が根底に流れて、暗く憂鬱な霧に覆われている。
冒頭の故郷の深い霧がそれをメタファーしている。イタリアの温泉の湯気などが続き、霧の映画の感があるし又、水の映画の感もある。要するに、湿っぽい風合いなのだ。
<欲望と精神性>
西側も節度ない欲望の果てが消費社会を生み、イタリアの川の水も汚れきっている。エウジニアは不倫も出来ないのかと巨大なおっぱいを出して罵倒し、彼の元を去る。
欲望に支配された世界と精神世界を象徴するカソリックへの回帰、糸口が見つからず焼身自殺するドメニコ。第九の合唱が響く(シラーの人類救済の歌)。
アンドレイは強迫観念に晒され、心臓病が悪化、息も絶え絶えである。
<映像美>
モノクロシーンと薄いカラーシーンがカットごとに使い分けられている。
多分、夢の中や回想、過去の出来事などはモノクロで、現在進行形がカラーなのだろう。
教会内のエウジニアの長い髪に斜光ライティングが当たり、まるで泰西名画、
他の場面でも多用されている。カメラが動かない長いカットだから、静止画の連続の感があり、美術館にでも行った気分。本作も、火、水、犬、白い馬、水の音、ローソク、廃墟などおなじみも登場、一言で映像美と言うけれど見てみなければ分からない、奇跡に近い(鏡の方が上と思うが)。特に、水辺で本を燃やす場面の炎の青白さが印象的。
<世界の救済>
監督は世の中の絶望に苦しむ人を撮っただけなのだろうか、それでは制作の意味が無いだろうに。
狂人こそ真実だとも言っている。これはドンキホーテと同じ主張。
表面に出さないプラトニックな愛は忘れないともいっている。肉体を否定これはカソリック的。
国境を無くせ とも言っている、その後EUが出来たが如何?
<自由>
通訳に言われる ロシア人は自由になっても自由の使い方を知らない、体験が無いからと(当時ペレストロイカで検閲が緩くなっていた)。
でも監督(アンドレイ?)はドメニコに民衆に向かった演説の中で もっと自由に生きろ と叫ばせている。自由て何なのか、当時のソヴィエトでは希求の代名詞であったろうが、西側でも本当は誰にも分から無いのだが。
<奇跡への期待>
ローソクを消さずにプールを3回目に横切れた。約束は守れたが奇跡は起きなかった。
ノスタルジアの中に静に死を迎えるアンドレイ。
<自殺>
そうこのイタリア旅行は18cのロシアの音楽家サスノフスキーの伝記を書くための取材旅行だった。彼も自殺した。
カソリックでは自殺は禁じられている。自分の命は神に委ねられている。死は未来であり、何時死ぬかを自己が正確に予見することは不可能。明日は核戦争が起きるかもしれない、大恐慌に襲われるかもしれない。未来はもともと生きている人間にとって知り得ない世界、神のみぞ知る。能力の及ばない領域だから、神様に委ねるしかない。先行きをあれこれ心配しても意味がない。未来は永遠に存在しない。
今最善を尽くすだけ、それだけを考えれば良い。その策が的確か否かは神が判断する。意図に反して神は冷たいかも知れないが。文句は言えない。
アンドレイは終始考え込んで、塞いでいる。
嘆いているのではなく、今 何をすべきか悩んでいるのだろうか。
信心深いドメニコも焼身自殺、焼身は社会に対するプロテスト、でも地獄に落ちるだろう。
宗教は現世否定が定理、現世が乱れ、救いがなくても、あの世で幸せが待っている。
今悩まなくても良い、信心深い人は現世でも幸せである。
でもアンドレイは信仰心はないようだ、教会に行かない、精神世界に憧れてはいるが、遁世の方向を向いている。
ノスタルジアに浸りながら、死を夢みる動けない自己、舞台は廃墟、亡びの美学・・静謐なエンディングではある。
この作品は(他のタルコフスキー作品も)謎だらけだが、何故か強く印象に残り、あ~だこ~だと考えさせる。そして、こんな長い文章を書かせてしまうマジック。
そこが魅力の源かも。

No.2
しあわせの隠れ場所 ☆4.0
2009/128 米 catv
J・L・ハンコック 監督
サンドラ・ブロック(L・A・デューイ、本作でオスカー主演女優賞、G・G 女優賞)
クィントン・アーロン(オアー)、ティム・マッグロー(S・デューイ)、キャッシー・ベイツ(家庭教師)
サンドラ45歳の作品だがまだまだ魅力的、はじけた演技でぐいぐい引っ張り、まるで一人芝居のようだった。
世の中カカァ殿下が多い、この金持ち一家もそうで夫も超理解者である為、奥様の世話好きが高じて身寄りのない黒人青年を引き取って世話をするという実話である。
しかも舞台は差別が残っている南部だから、大変な勇気と言うべきだろう。
最後はMFLのドラフトで1位指名されるが、青年が幼少時に負った疵の深さが語られことによりデューイの成し遂げた事の偉大さが際立ち、ドラマティックな構成になっている。
実の二人の子供たちも周りから白い眼で見られても、この青年を信頼している姿も微笑ましい。でも余りに両親、家族、多くの知人がこの変わった黒人を擁護しているので、実話とは言え脚色の匂いがしてしまうのは事実だ。
それでも作品の評価が良いのは、何といってもハッピーエンドだという事、人は信頼できるという楽観論だから悪人は登場しないこと、だからひやひやせずに安心して楽しめることだろう。
正当なハリウッド映画と言って良い。こんな映画ばかりだと問題だが、こんな映画も必要なのだ、人生は余りにもつらいのだから。

No.1
ギフテッド ☆4.0
2017/米/101分 角川シネマ新宿 1.10
マーク・ウエブ 監督 トム・フリン脚本
クリス・エヴァンス(主役のフランク、メアリーの叔父)
マッケンナ・グレース(メアリー、7歳の天才少女)
リンゼイ・ダンカン(イブリン、フランクの母親)
ジェニー・ストレート(ボニー、普通小学校の教師、フラ
ンクの恋人)
オクタビア・スペンサー(ロバータ、黒人のお手伝い)
親子の別れと再会と言う伝統的な話は、どれも泣かされるものだが、本作も思わず泣かされた。この場合正確には親子でなく叔父と姪という間柄だが、二人だけで暮らして(いや片目のフレッドという猫を入れると3人)いるから、実質的には親一人子一人という親密な関係だ。
7歳のメアリーはギフテッド、数学の天才である為、祖母は遠隔地の英才学校に行かせようと目論んでいる。でもこの祖母は名誉信が強く子供(フランクの妹/天才数学者)の心を無視し、自殺に追いやったことでフランクとは絶縁状態、裁判沙汰で引き離しにかかる。
よくよく考えると本作はギフテッドという特殊な題材を除いては大して珍しいシナリオでは無い。でも一つだけ感心させられたのは、自殺した妹が兄に託した論文は数学会で解けない難題を解いた世界的業績だったが、これを親の死んだ後に公表するよう遺言していた事だ。
自分を追いやった親に名誉心を満足させたくないという子供の恨みに、親の罪の深さを垣間見た。
ギフテッドはある能力では飛び抜けているが、一般学校では運動についていけなかったり、協調性が無かったりするらしいので、あながち特殊教育が悪いわけではない。
住んでいるのはフロリダ・タンパ、エンディングではマサチューセッツ工科大学で7歳の子供が大学生と一緒に講義を受けた後、母校の小学校に友達と遊ぶために寄っている。通える距離ではないので、聴講生だったのか?良く分からない結末だった。
もしこれが、イヴリンの思惑通りマサチュセッツの教授に預けられた後の一時帰省だとしたら、論旨が一貫せず裏切られた感じがするが。
カナダにも日本人のギフテッドがいて、各大学が取り合いをしているらしい。
確率的に必ず生まれる。親はどう対処すればいいのだろう。普通の人間を目指すのか、モンスターにするのか。世界の発展のためという言葉も使われている、責任重大だ。
メアリーの可愛さにお手上げ。
 荻虫(tekicyu)のつぶやき
荻虫(tekicyu)のつぶやき